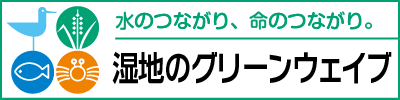日本の湿地保全と司法
ラムネットJ共同代表 堀 良一
1 日本の環境訴訟の課題
日本の環境訴訟の本格的な取り組みは,1960年代後半の4大公害訴訟に始まる。それらは公害による被害者の事後的な救済を求める損害賠償請求訴訟であった。それらの訴訟は,判決による被害の認定を契機にした恒久的な被害対策制度を求める運動へと発展した。そして今,日本の環境訴訟は,被害を生み出さないための,環境破壊の事前差し止めや,環境再生を課題としている。
以下,日本の環境訴訟の現段階の問題状況を特徴的に表している3つのケースを報告する。
2 ケース1:よみがえれ!有明訴訟
国が地元自治体の支援を受けて行う諫早湾干拓事業に反対して提起された訴訟である。
破壊される有明海の諫早湾干潟と浅海域は,日本最大級の規模を持ち,日本有数の漁場である有明海漁業をはぐくみ,東アジアにおける渡り鳥のルートを維持する上で欠くことのできない湿地であった。
この訴訟は漁業被害が顕著になった2002年11月に提起された。その時点で事業は94%終了していたので,事業の終了間際に,訴訟の目的は工事の差し止めから,環境再生を目指す,潮受堤防の撤去,それが困難な場合は,少なくとも潮受け堤防の排水門を開門すべきであるというものに変更された。事業が終了した2008年6月に地方裁判所で開門を命じる判決が言い渡され,この判決は,2010年12月に高等裁判所でも支持され,最高裁判所に上告されることなく確定した。
判決は,判決確定から3年以内に準備工事を行い,潮受堤防排水門を開門することを命じるものであった。開門の期限は2013年12月である。
ところが,共に事業を推進してきた地元自治体の反対を理由に,国は,いまだ準備工事に着手していない。このままでは2013年12月の開門は不可能という事態を招きかねないのが現状である。
地元自治体が国に,確定した判決を履行しないように求め,国がそれを理由に確定判決の履行をサボタージュするという,法治主義や三権分立という民主主義社会の基本構造を否定する異常事態が出現している。
3 ケース2:泡瀬干潟埋立差し止め訴訟
自治体が主体になり国とともに泡瀬干潟およびその周辺藻場を埋め立てようとする事業に反対して提起された訴訟である。泡瀬干潟は沖縄本島にあり,南西諸島を代表する干潟と藻場が広がる重要湿地である。訴訟は,2005年5月に自治体を相手として,事業への公金支出差し止めを求めて提起された。争点は,埋立事業による環境破壊と事業の経済的合理性の存否であった。
2008年11月に地方裁判所は,埋立事業には経済的合理性がないと判断して,自治体の公金支出を差し止め,この判決は2009年10月に高等裁判所でも支持され確定した。
ところが,埋立を行う自治体は埋立地の土地利用計画を変更して,埋立を継続している。
本来,埋立は,特定の土地利用のために行われる。当初の目的が否定されたら,今度は目的を変えてでも埋立だけは継続しようという自治体のあり方は,当然のことながら,厳しく批判されている。司法判断の抜け穴をかいくぐるような埋立事業に対して,変更後の土地利用計画もまた経済的合理性がないとして,再び,住民による事業への公金支出差し止め訴訟が提起されているところである。
4 ケース3:上関原発損害賠償事件
瀬戸内海にある上関の海域は,日本を代表する良好な自然環境であり,漁場である。その上関の海域を埋め立て,原子力発電所を建設しようとする計画に対して,20年以上もの間,反対運動が繰り広げられている。反対運動を行っているのは,漁場を破壊され原子力発電所の危険にさらされる漁民と,瀬戸内海に残された良好な自然環境を保全しようとする市民たちである。
この裁判は,反対運動を行っている漁民や市民の中心人物4人を相手に,2009年12月に事業者である電力会社から提起された。求められたのは,埋立工事妨害を理由とする損害の賠償である。請求額は当初4800万円であったが,その後,3900万円に変更されている。
いざ訴訟が始まってみると,電力会社は,被告にした4人の漁民や市民がどのような行動を行ったかを特定しておらず,また,損害額も確定しないまま提訴したことが明らかになった。そのため,電力会社は,そもそも損害の賠償が目的ではなく,原子力発電所建設への反対運動を押さえ込むために,訴訟を起こしたのではないかと批判されている。
2011年3月11日に,世界を震撼とさせた福島の原子力発電所事故が起こり,漁民や市民の反対運動が正しかったことが悲惨な結果によって証明されたにもかかわらず,電力会社は上関原子力発電所建設を中止しようとせず,相変わらず,この裁判を継続させようとしている。
5 環境保全に役立つ司法が求められている
ケース1やケース2のように,近年の環境保全の要請に応えるような判断が,ようやく日本の司法においても見られるようになってきた。ところが,その司法の判断を無視する行政への対応が,環境保全と司法に関する新たな課題として登場している。
ケース3のように,環境保全運動を押さえ込むために司法が悪用されるケースもある。
このような状況では,市民の司法へのアクセスが保障されているとは,到底,評価できないことは明らかである。
国際社会は,オーフス条約を制定して,環境に関する情報へのアクセス、環境に関する政策決定過程への参加、環境に関する司法へのアクセスの3分野において、各国内の法制度の整備を促そうとしている。しかしながら,日本はオーフス条約をいまだに批准していない。
今回紹介した3つのケースは,オーフス条約の批准と同条約が目的としている司法へのアクセス権を実質的に保守する法制度の整備,および,環境保全に役立つ司法への転換が,日本において,強く求められていることを示している。
※この記事は、ラムサールCOP11向けて発行した「ラムネットJニュースレター」号外(英語版)に掲載した記事の日本語の元原稿です。
2012年07月08日掲載